日本の農業の原風景
「軒先養豚、庭先養鶏」
軒先の囲いで残飯を餌とする豚を飼い、庭先ではミミズや昆虫を餌に鶏を飼う。そして日本古来の労役用の小型の牛が田んぼを鋤く。現代ではまず見ることのできない懐かしい風景は、一枚の絵のようですね。

このころの鶏はすべてが卵肉兼用種で、海外から明治の初期に導入されました。まずは卵を採り、盆暮れ、またお祝いごとなどのときにお肉としていただきます。
養鶏とは言っても農家の家庭生活の範囲内でできますが、このコーナーで取り上げてきた「よい雛、よい餌、よい管理」の「よい管理」には当たりません。これらは農家の家業であり、畜産業ではないからです。

管理のルーツは「サムライ養鶏」
尾張藩では武士の内職として鶏が飼われており、明治維新後も職を失った士族が養鶏をしていました。その中でも海部壮平・正秀兄弟は、血のにじむような努力の末「名古屋コーチン」を生み出しました。このころの飼育施設は平飼いの開放鶏舎であったはずです。自家用にとどまらず営業用として用いられた施設での飼育、これが「管理のルーツ」と考えます。

「よい管理」の原点は、
卵と肉の専用種開発にあり
産業として大きく養鶏が発展したのは、戦後卵用鶏・肉用鶏と、鶏が専用種に分かれてからです。そして乳牛の管理と肉牛の管理が違うように、卵用鶏と肉用鶏の管理も違います。
卵用鶏の管理に「ケージ飼育」があります。鶏舎内の収容羽数は増加し、作業性も効率もよくなり、大量飼育が可能になりました。今では動物愛護の観点から問題視されることもあるケージ飼育ですが、導入時の目的達成の意味では「よい管理」であったと思います。卵用鶏の管理としては、その後ウインドウレス(窓無し)鶏舎が初めて登場しました。

一方、卵用鶏よりも遅れて発展した肉用鶏は、鶏の疾病コクシジウム症を避けるために木や竹で作ったバタリー、いわば檻で飼育していました。これも管理面で「胸だこ」など難点があり現代では見られなくなりました。1960年代、アメリカからインテグレーション(統合管理・運営)生産が導入され、大量生産時代になると、その管理方法は大量羽数の平飼いとなります。現在見られる肥育用のウインドウレス鶏舎で、給餌、給水も自動システムで管理するようになりました。従来の方法よりも一歩進んだ「よい管理」の定番が完成したと言えるでしょう。

現代鶏舎の「よい管理」、
そして協会の考えとは
高度経済成長期後半になると、生協運動や学校給食の発展で安心・安全への意識が高まり、バブル景気の影響で味のよい「グルメ鶏」志向へと時代の嗜好が移り変わりました。そして銘柄鶏が、またJAS地鶏が登場しました。
JAS地鶏には「平飼い、1平方メートルあたり10羽以下」という明確な管理規定があります。当然ながら、よい管理が安心・安全へとつながる表れでしょう。

ここで「よい管理」の基礎は舎内の換気であるとお伝えしておきます。少羽数飼育は自然が管理してくれますが、大量羽数の一カ所管理には、高度な科学技術と円熟したオペレーションが必要で、十分な酸素の供給、適温、適湿、床面の乾燥、機器の適切な運用など多くの要素をマスターすることが大切です。
現代ではIoTを活用し、鶏舎の温度や湿度、環境面も管理できるシステム鶏舎が導入されるようになってきました。こうして第6回で述べた「よい雛」や、第8回で取り上げた「よい餌」も、「よい管理」により、その能力を十分に発揮できるようになったのです。

現代鶏舎の「よい管理」、
そして協会の考えとは
このように「よい管理」は時代とともに進化してきましたが、日本赤鶏協会が考える「よい管理」は、単に鶏舎や鶏の飼育管理にとどまりません。
赤鶏の本質を理解し、その価値を発信してみなさまの暮らしに役立てていただく過程を、協会の究極の「よい管理」と捉えています。
次回はいよいよ最終回、「よい管理」後編へと続きます。

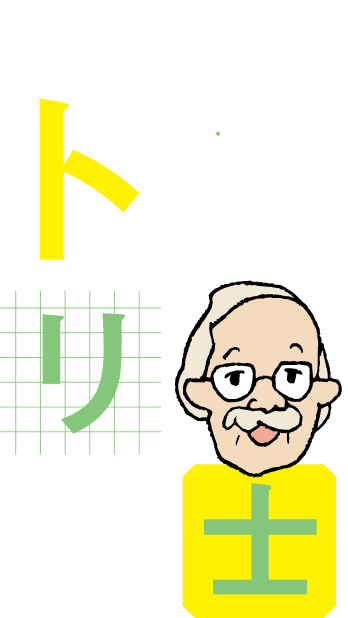
![[第9回] よい鶏づくり3カ条その3「よい管理」前編](https://nippon-akadori.or.jp/wp/wp-content/uploads/hero-column9.png)
